|
|
|
|
|
|
|
|
東京都写真美術館 |
<目 次> |
|
天と地の共鳴 バラ色にかがやく絶壁、天空にうつしだされる山影、ここは天と地の共鳴の現場である。 2003年8月、東京都写真美術館(東京・恵比寿)で開催された白川義員写真展「アルプスから世界百名山へ」にいく。冒頭の写真は、日の出直後、酸素マスクをつけて8600mの高度で航空機の窓をあけて撮影したエベレストの東壁だという。 白川義員(しらかわよしかず)さんは、「地球再発見による人間性の回復」をテーマに、荘厳で神秘的な風景を被写体としておいもとめ、「アルプス」「ヒマラヤ」「アメリカ大陸」「聖書の世界」「中国大陸」「神々の原風景」「仏教伝来」「南極大陸」を発表、そして2002年に、彼の山岳写真の集大成となる前人未踏の「世界百名山」を完成させた。この展覧会は、この最新作「世界百名山」を紹介するものである。ほとんどの作品は、上空7000m以上の航空機の中から、酸素マスクをつけてその窓をあけて撮影した肉迫撮影ということだ。 世界百名山の選考基準は解説によると以下の通りである。 1.雄大、壮大、荘厳であること。鋭さも必要だが、なによりも品性多角、格調たかい山であること。 写真美術館2階の展示室では、まず、ネパール・ヒマラヤの数々の巨大な山容がせまってくる。サガルマータ(エベレスト)、マカルー、カンチェンジュンガ、ローツェ、チョー・オ・ユー、マナスル、アンナプルナ、ダウラギリ。ヒマラヤを愛する者なら誰もがしっている8000m級の高山が次々にあらわれてくる。太陽の光によってかがやくこれらの山々は、大地の壮大なうねりもあらわしている。 ネパール・ヒマラヤをぬけると、アラスカの山々が、そしてアンデスの山々がひろがり、パキスタン、ヨーロッパ、アフリカ、インド、中国、ロシアと、天空と大地がおりなすかがやかしい世界がつづいていく。最後は日本の富士山である。世界の名山を「体験」したあとで富士山をながめると、その容姿のうつくしさにあらためて気づかされる。
天と地の二つの視点 百名山の峰々は、まさに天空と接している。天空からみると、山全体を一瞬のうちにとらえることができ、山々がつくりだす世界を一望のもとにおさめることができる。それは、それぞれの朝夕の一瞬にうちに鮮烈に彩色される世界であり、その「一瞬の光景」の中にすべてが存在しているのである。 そして一方で百名山は、山麓を大地へとのばし、大地に根をおろしている。これらの山々は、大陸移動と造山運動がおりなす悠久の自然史の「結果」であり、そこには大地の長大な歴史があることをおしえてくれる。 このように、百名山は天空と大地とをつなぎ、天空からみる「天の視点」と大地からみる「地の視点」という二つの視点を明瞭にあたえてくれる。百名山は天と地の共鳴の現場である。 「天の視点」により、その世界の構造全体を一瞬のうちにみることができ、これは、空間的地理的なものの見方であり、すべてを「こえる」見方、直観的な見方といってもよい。一方「地の視点」により、その世界の時間的流れを順番に想像することができ、これは、時間的歴史的なものの見方であり、ひとつひとつを「たどる」見方、論理的な見方といってもよい。(図1)
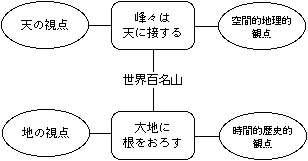
図1.百名山は天と地とをつなぐ
そして、これら二つの視点は、「航空写真の判読」と「フィールドワーク」という二つの方法論へと具体化することができる(図2)。 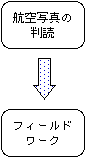
図2.航空写真判読からフィールドワークへ
ある世界をしらべる場合、あらかじめ航空写真をよくみて全体像を一気につかんでおき、その上でここぞというフィールドにおりていくのがよい。全体をみて部分に入るということである。航空写真によってえられた全体的なイメージをたえずえがきながら、フィールドワークでは時間をかけて大地を実際にたどり、現場でえられた個々の情報を全体的イメージの中にうめこんでいく。そして、えられた情報をくみたててその世界の歴史を考察する。こうして、写真判読とフィールドワークとは相互に補完しながら、われわれをよりふかい認識へとみちびいてくれる。 今回、この壮大荘厳な百名山に接して、グローバルなスケールであらたな角度から地球をとらえなおすことができ、「天の視点」と「地の視点」の重要性についておしえられた。地球再発見のために、白川さんのすばらしい写真の数々を今後とも活用していきたいものである。 |
|
|
|
|
|
(C) 2003 田野倉達弘